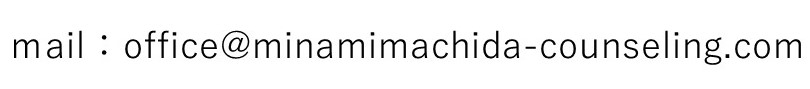5月24日に「精神分析におけるセックスとジェンダーを学ぶ会2023」第2回を行いました。今回はジーン・ベーカー・ミラーの『イエス・バット』を扱いました。
Miller,J.B. 1976 Toward a New Psychology Woman. Beacon Press. 河野貴代美監訳(1989)『イエス
バット(Yes,But…)――フェミニズム心理学をめざして』新宿書房
本書はアメリカで長く読まれ続けた書籍で、「女性的価値を擁護しながら男性社会に進出しようとする人々」のバイブル的存在となったと言われています。内容的には、本来、人間はみな支えられケアされる関係性の中に生きているという主張のもと、これまでの精神分析は「分離した自律的自己を発達のゴールとするもの」とされてきたことを批判し、実際には精神分析は「女の仕事」をしてきたにもかかわらず、そのようには認識されてこなかったと鋭く指摘するものでした。
「女の仕事」とは、不快で手に負えなく、汚いと思われている身体の部分や身体にまつわることがらを、ここちよく清潔に整える仕事のことで、具体的には家事、育児が挙げられています。看護、介護もそこに含まれるでしょう。
誤解を招いてはいけないのではっきりと申し上げておきますが、私自身も本書の著者も、これらの仕事を「女のするべき仕事」とは考えていません。「女の仕事」という表現が用いられているのは「これまで主に女が担わされてきた仕事」という意味だろうと思います。
精神分析は人のこころに対してこのような仕事をしてきた。なぜならそれが人間にとって根源的に必要なものだから。にもかかわらずそのことを否認してきた歴史があるのは、分離や自律を過度に重視する「男の仕事」の達成こそが重要であり、「女の仕事」を軽視しがちな認識が精神分析にも社会にもあるのではないか。著者の主張は概ねこのようなことだろうと思います。
ディスカッションでは、著者があまりに「女の仕事」を強調し、「男の仕事」の重要性を否認しているのではないかという意見もありました。
本書が書かれたのは1976年。1960年代に生じた第2波フェミニズムと1990年代の第3波フェミニズムの合間に生まれた著作と言えます。第2波フェミニズムでは女性も政治や社会活動に進出すべく、やや過激とも言える(その必要性があってのことですが)、女性の強さの誇示がありました。一方で1990年代には多様性という視点が取り入れられ、「フェミニストならこうあるべき」と決めつけるのではなく、個人の自由を重視する流れとなりました。つまり、その女性自身が選び取ったのであれば古典的な女性的生き方をも肯定するという価値観です。
本書がこの波の間に生まれたというのは興味深く思います。もし、精神分析が分離や自律だけを重視する「男の仕事」の達成こそが重要だとするものであるならば、女だって「男並み」に政治や社会に参加できる!という第二波フェミニズムと同じものであると言えるでしょう。このような世界観では「男並み」というマッチョなあり方がデフォルトであることが暗黙の了解となっています。これに対して、性別がどうあれ人はみなケアを求めていて、分離や自律だけが達成ではない、精神分析はそこに寄与してきたのではないかということを本書は投げかけているのだと考えられます。
たしかに本書は「女の仕事」を重視しすぎる傾向があります。精神分析の仕事は、ケアだけではなくセラピーでもあります。母性だけではなく、当然ながら父性も必要です。そのことに一切触れていないのは偏りを感じますが、第二波から第三波への移行期であることを考えると、時代的には必要な主張だったのだろうと思われました。
また私個人としては、精神分析的臨床は女の仕事「も」するし、ケア「も」すると考えています。それらは男の仕事やセラピーを行おうとするなら切り離すことはできないと思います。そういう点では重要な部分に光を当てた文献だと思います。
ただし、実はこのような視点は当時すでに精神分析理論の中に存在していました。本勉強会でも2021年度に取り上げましたが、ウィニコットは「男性的要素/女性的要素」「Doing/Being」に関する論文で、「女性要素」「Being」こそ基礎であり「創造性」の元となると述べています。特に、男性が女性との同一化に抵抗するのは「女性に委任してきた自分自身の経験の一部を取り戻そうとしている」、「男性が自分のなかのこれらの部分を十分に統合し、よりよく再統合すれば、大きな快感と成長を得るだろう」と言う主張は、ほとんど同じことを1971年にウィニコットが述べています。にもかかわらずまったく引用していないのは、ちょっと著者が不勉強だったのかもしれません。誰であってもすべてを知っているわけではないし、私も人のことは言えないのですが、がんばりましょうね…と思いました。